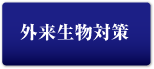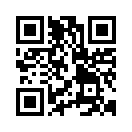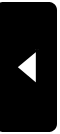2017年06月04日
【外来種シンポジウム】を開催いたしました!
みんなのはままつ創造プロジェクト2017採択事業
【とって食べる】 by昆虫食倶楽部
5月28日(日)に【外来種シンポジウム〜外来種って悪者なの? 生物多様性ってなに?】を開催しました!

会 場:佐鳴会館会議室
参加者:90名
当日は、とても良い天気のアウトドア日和で、自然好き、生き物好きの人は外遊びをしたい日だったと思いますが、それにもかかわらず、インドアの勉強会に90名もの大勢の方に参加していただきました。
ありがとうございます。
とても嬉しいです。
【とって食べる】の活動を続けている中から、
「自然や生きものっておもしろいな」と思うのと同時に、
「自然や生きものについてもっと深く知りたい」と思うようになりました。
さらに、私たちにさまざまな恵みを与えてくれる自然を持続可能なものにするためにできることがあるならば、積極的に取り組んでいきたい、と思うようになりました。
今回は、様々な利害が絡み合い複雑な問題になっている「外来種問題」について、一度問題を整理しながら、みんなでじっくり考える機会を設けたい、と思いこのシンポジウムを企画しました。

浜松市環境政策課の鈴木良実さん
「浜松市の外来種の現状と取り組み」
浜松市は山、川、海、湖、森林、砂浜…多種多様な自然環境のもと、とても生物多様性が豊富な地域です。
浜松市として、今はアライグマとクリハラリス(タイワンリス)に集中的に取り組んでいるとのこと。
昆虫食倶楽部のミシシッピアカミミガメの取り組みについてもとても注目し、協力してもらっています。

認定NPO法人生態工房の片岡友美さん
「アカミミガメの問題と対策」
生態工房さんは、東京の公園で長年アカミミガメの対策に取り組んでいます。
アカミミガメがなぜこんなにも増えてしまったのか、その歴史的経緯から始まり、
それに伴い、行政はどんな取り組みをしてきたのか、
生態工房としてどんな取り組みをしているのか、
私たちはアカミミガメに対してどのように向き合うのがよいか、
といったことを、実際の取組みに基づき、とてもわかり易くお話していただきました。
改めて経緯を見てみると、アカミミガメがここまで増えてしまって、問題が深刻化してしまった原因は、
需要があるからと安易に持ち込み、大量にばらまいてしまったこと、
ペットとして飼うことに関する知識(かなり大きくなるよ、とか)の不足など、
人間側の問題が改めてうかびあがってきます。
アカミミガメから学んだ私たちはこの「失敗」を繰り返してはいけません。
そして、今現在アカミミガメを飼っていらっしゃる方(相当多いと思われます)は、
今後も末永くかわいがって大切に飼い続けてくださいね。

静大工学部准教授の戸田三津夫さん
「生物多様性とは」
そもそも外来種を駆除することで守るべき「生物多様性」とは一体何なのか
30数億年というとてつもなく長い時間をかけて生態系と生物、生物多様性がかたちづくられてきました。
現在おびただしい数の生物が生存していますが、そのどれもが奇跡の結果生まれてきたものです。
人間もその奇跡(偶然)のうちの一つに過ぎないのですが、
その人間が「外来種問題」を起こし、生物多様性がどんどん失われている状況です。
この問題を考えるときには、まずはそこをしっかりと抑えておきたいです。
その他、生物多様性について、なぜ生物多様性を守らないといけないのか、比喩もまじえながらとてもわかりやすく発表していただきました。
それぞれの登壇者のプレゼンテーション内容は、とてもブログですべてを表すことは出来ませんが、雰囲気だけでも伝わればと思います。

プレゼンテーションのあとに予定していたパネルディスカッションは、残念ながら時間切れでカットとなってしまいました。
アンケートではパネルディスカッションを楽しみにしていたという意見が多かったので、ぜひ改めてその機会を設けたいと思っています。

長年佐鳴湖でカメを含む様々な生物の調査を続けている藤森さん
佐鳴湖周辺にはまだまだ在来のイシガメがたくさん生息しているとのこと。
であるからこそ逆にアカミミガメの対策を速やかに進めていきたいです。

ふじのくに地球環境史ミュージアムの岸本さん
最近「外来種も在来種の仲間に入れてもいいじゃないか」といったような雰囲気が出てきていることを危惧しているとのこと。
このあたりもパネルディスカッションで掘り下げていきたかったです(次回是非やりましょう)
最後に
私たち昆虫食倶楽部は、
外来種は「悪者」ではない。忌み嫌ってもいない。
が、生物多様性を守っていくためには外来種の駆除は進めていかないといけない。
というのが基本的スタンスです。
それが世の中のスタンダードになっていったらいいと思っています。
そしてそれに基づいてこれからも丁寧に活動していきます。
一方で、そうは思っていない方や、「ほんとに駆除してしまっていいのかな」ともやもやしている方がいらっしゃることも承知しています。
また今回のような外来種問題についていっしょに考える機会を作っていきたいと思いますし、
もうひとつは、【とって食べる】のイベントで”食べる”という体験が、考え方が違う人同士をを繋いでいくきっかけになる可能性がある、と期待しているのですが、いかがでしょうか。
↓こちらも読んで下さい
共同主催者のNPO法人浜松NPOネットワークセンターのブログ
協賛いただいたSaveJapanプロジェクトのページ
とる食べ会員募集中です!
詳しくはこちら←クリック
【お問い合わせ先】
昆虫食倶楽部 夏目恵介
電話:090-9900-0928
メール:tottetaberu@gmail.com
【とって食べる】 by昆虫食倶楽部
5月28日(日)に【外来種シンポジウム〜外来種って悪者なの? 生物多様性ってなに?】を開催しました!

会 場:佐鳴会館会議室
参加者:90名
当日は、とても良い天気のアウトドア日和で、自然好き、生き物好きの人は外遊びをしたい日だったと思いますが、それにもかかわらず、インドアの勉強会に90名もの大勢の方に参加していただきました。
ありがとうございます。
とても嬉しいです。
【とって食べる】の活動を続けている中から、
「自然や生きものっておもしろいな」と思うのと同時に、
「自然や生きものについてもっと深く知りたい」と思うようになりました。
さらに、私たちにさまざまな恵みを与えてくれる自然を持続可能なものにするためにできることがあるならば、積極的に取り組んでいきたい、と思うようになりました。
今回は、様々な利害が絡み合い複雑な問題になっている「外来種問題」について、一度問題を整理しながら、みんなでじっくり考える機会を設けたい、と思いこのシンポジウムを企画しました。
浜松市環境政策課の鈴木良実さん
「浜松市の外来種の現状と取り組み」
浜松市は山、川、海、湖、森林、砂浜…多種多様な自然環境のもと、とても生物多様性が豊富な地域です。
浜松市として、今はアライグマとクリハラリス(タイワンリス)に集中的に取り組んでいるとのこと。
昆虫食倶楽部のミシシッピアカミミガメの取り組みについてもとても注目し、協力してもらっています。
認定NPO法人生態工房の片岡友美さん
「アカミミガメの問題と対策」
生態工房さんは、東京の公園で長年アカミミガメの対策に取り組んでいます。
アカミミガメがなぜこんなにも増えてしまったのか、その歴史的経緯から始まり、
それに伴い、行政はどんな取り組みをしてきたのか、
生態工房としてどんな取り組みをしているのか、
私たちはアカミミガメに対してどのように向き合うのがよいか、
といったことを、実際の取組みに基づき、とてもわかり易くお話していただきました。
改めて経緯を見てみると、アカミミガメがここまで増えてしまって、問題が深刻化してしまった原因は、
需要があるからと安易に持ち込み、大量にばらまいてしまったこと、
ペットとして飼うことに関する知識(かなり大きくなるよ、とか)の不足など、
人間側の問題が改めてうかびあがってきます。
アカミミガメから学んだ私たちはこの「失敗」を繰り返してはいけません。
そして、今現在アカミミガメを飼っていらっしゃる方(相当多いと思われます)は、
今後も末永くかわいがって大切に飼い続けてくださいね。

静大工学部准教授の戸田三津夫さん
「生物多様性とは」
そもそも外来種を駆除することで守るべき「生物多様性」とは一体何なのか
30数億年というとてつもなく長い時間をかけて生態系と生物、生物多様性がかたちづくられてきました。
現在おびただしい数の生物が生存していますが、そのどれもが奇跡の結果生まれてきたものです。
人間もその奇跡(偶然)のうちの一つに過ぎないのですが、
その人間が「外来種問題」を起こし、生物多様性がどんどん失われている状況です。
この問題を考えるときには、まずはそこをしっかりと抑えておきたいです。
その他、生物多様性について、なぜ生物多様性を守らないといけないのか、比喩もまじえながらとてもわかりやすく発表していただきました。
それぞれの登壇者のプレゼンテーション内容は、とてもブログですべてを表すことは出来ませんが、雰囲気だけでも伝わればと思います。

プレゼンテーションのあとに予定していたパネルディスカッションは、残念ながら時間切れでカットとなってしまいました。
アンケートではパネルディスカッションを楽しみにしていたという意見が多かったので、ぜひ改めてその機会を設けたいと思っています。
長年佐鳴湖でカメを含む様々な生物の調査を続けている藤森さん
佐鳴湖周辺にはまだまだ在来のイシガメがたくさん生息しているとのこと。
であるからこそ逆にアカミミガメの対策を速やかに進めていきたいです。
ふじのくに地球環境史ミュージアムの岸本さん
最近「外来種も在来種の仲間に入れてもいいじゃないか」といったような雰囲気が出てきていることを危惧しているとのこと。
このあたりもパネルディスカッションで掘り下げていきたかったです(次回是非やりましょう)
最後に
私たち昆虫食倶楽部は、
外来種は「悪者」ではない。忌み嫌ってもいない。
が、生物多様性を守っていくためには外来種の駆除は進めていかないといけない。
というのが基本的スタンスです。
それが世の中のスタンダードになっていったらいいと思っています。
そしてそれに基づいてこれからも丁寧に活動していきます。
一方で、そうは思っていない方や、「ほんとに駆除してしまっていいのかな」ともやもやしている方がいらっしゃることも承知しています。
また今回のような外来種問題についていっしょに考える機会を作っていきたいと思いますし、
もうひとつは、【とって食べる】のイベントで”食べる”という体験が、考え方が違う人同士をを繋いでいくきっかけになる可能性がある、と期待しているのですが、いかがでしょうか。
↓こちらも読んで下さい
共同主催者のNPO法人浜松NPOネットワークセンターのブログ
協賛いただいたSaveJapanプロジェクトのページ
とる食べ会員募集中です!
詳しくはこちら←クリック
【お問い合わせ先】
昆虫食倶楽部 夏目恵介
電話:090-9900-0928
メール:tottetaberu@gmail.com
Posted by 昆虫食倶楽部 at 11:25│Comments(0)
│開催したイベントの報告