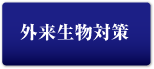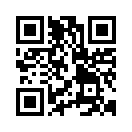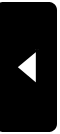2019年06月15日
SAVEJAPANプロジェクト1回目、2回目開催しました。
【とって食べる】 by 昆虫食倶楽部

クサガメ
SAVEJAPANプロジェクトの1回目、2回目のイベントを開催しました。
1回目 5/19(日) アカミミガメ捕獲調査+外来生物勉強会
http://savejapan-pj.net/sj2018/shizuoka/report/post_3.html
2回目 6/9(日)アカミミガメ捕獲調査+解剖してみよう
http://savejapan-pj.net/sj2018/shizuoka/report/post_4.html
それぞれSAVEJAPANプロジェクトのホームページにレポートがアップされています。
ぜひ読んでみて下さい!

アカミミガメの捕獲は3年目に突入し、捕獲から計測、記録までだいぶ段取り良く進めることができるようになってきました(最初の頃は手探り状態だったので、今思えばだいぶおぼつかない感じでしたねぇ)。

佐鳴湖にて700匹以上のアカミミガメを捕獲してきましたが、まだまだたくさんいます。
ちょっと減ったからといって捕獲をやめてしまうとまたすぐに増えてしまいます。
これからも楽しみながら継続していきたいです。

あらたに問題として浮上してきたのが、クサガメをどうするか問題。
クサガメは数百年前から日本にいるカメですが、中国からの外来種だということがはっきりしてきました。
問題は在来種のイシガメと交雑してしまうこと。
交雑が進むことで「純粋な」イシガメが絶滅してしまうことにつながる可能性があります。
関係機関と合意形成した上で駆除対象にしている地域もあるそうです。
佐鳴湖のクサガメをどうするか、話し合いの機会を作っていきたいです。
ハナガメとクサガメの雑種も捕獲されます。
雑種問題は、アカミミガメ以上に複雑でやっかいな問題かもしれません。

解剖実習には小学生から70歳以上の方まで幅広い年齢層の方々に参加していただきましたが、みなさんそれぞれ積極的に解剖に取り組んでいました。
今回は食べませんが、「(あたまの栄養として)いただきます!」の感謝の気持ちを込めて、丁寧に解剖しました
教育現場で解剖実習をする機会が減ってきているそうです。生徒たちの価値観や先生の負担を考えるとそれもやむを得ないのかな、と思う一方で、
実際に生き物を解剖して、内蔵を含めて手にとって見る経験は、自然に対する興味を深めるためにとても大切なことだと思います。
ご希望があれば、出張解剖実習対応しますので、ご相談下さい。
われわれスタッフ側もだいぶ段取り良く解剖実習を進めることができるようになってきました。


フェイスブック https://www.facebook.com/tottetaberu/
インスタグラム https://www.instagram.com/tottetaberu/
「いいね!」「フォロー」お願いしますm(_ _)m
とる食べ会員募集中です!
詳しくはこちら←クリック
【お問い合わせ先】
昆虫食倶楽部 夏目恵介
電話:090-9900-0928
メール:tottetaberu@gmail.com

クサガメ
SAVEJAPANプロジェクトの1回目、2回目のイベントを開催しました。
1回目 5/19(日) アカミミガメ捕獲調査+外来生物勉強会
http://savejapan-pj.net/sj2018/shizuoka/report/post_3.html
2回目 6/9(日)アカミミガメ捕獲調査+解剖してみよう
http://savejapan-pj.net/sj2018/shizuoka/report/post_4.html
それぞれSAVEJAPANプロジェクトのホームページにレポートがアップされています。
ぜひ読んでみて下さい!

アカミミガメの捕獲は3年目に突入し、捕獲から計測、記録までだいぶ段取り良く進めることができるようになってきました(最初の頃は手探り状態だったので、今思えばだいぶおぼつかない感じでしたねぇ)。

佐鳴湖にて700匹以上のアカミミガメを捕獲してきましたが、まだまだたくさんいます。
ちょっと減ったからといって捕獲をやめてしまうとまたすぐに増えてしまいます。
これからも楽しみながら継続していきたいです。

あらたに問題として浮上してきたのが、クサガメをどうするか問題。
クサガメは数百年前から日本にいるカメですが、中国からの外来種だということがはっきりしてきました。
問題は在来種のイシガメと交雑してしまうこと。
交雑が進むことで「純粋な」イシガメが絶滅してしまうことにつながる可能性があります。
関係機関と合意形成した上で駆除対象にしている地域もあるそうです。
佐鳴湖のクサガメをどうするか、話し合いの機会を作っていきたいです。
ハナガメとクサガメの雑種も捕獲されます。
雑種問題は、アカミミガメ以上に複雑でやっかいな問題かもしれません。

解剖実習には小学生から70歳以上の方まで幅広い年齢層の方々に参加していただきましたが、みなさんそれぞれ積極的に解剖に取り組んでいました。
今回は食べませんが、「(あたまの栄養として)いただきます!」の感謝の気持ちを込めて、丁寧に解剖しました
教育現場で解剖実習をする機会が減ってきているそうです。生徒たちの価値観や先生の負担を考えるとそれもやむを得ないのかな、と思う一方で、
実際に生き物を解剖して、内蔵を含めて手にとって見る経験は、自然に対する興味を深めるためにとても大切なことだと思います。
ご希望があれば、出張解剖実習対応しますので、ご相談下さい。
われわれスタッフ側もだいぶ段取り良く解剖実習を進めることができるようになってきました。


フェイスブック https://www.facebook.com/tottetaberu/
インスタグラム https://www.instagram.com/tottetaberu/
「いいね!」「フォロー」お願いしますm(_ _)m
とる食べ会員募集中です!
詳しくはこちら←クリック
【お問い合わせ先】
昆虫食倶楽部 夏目恵介
電話:090-9900-0928
メール:tottetaberu@gmail.com
Posted by 昆虫食倶楽部 at 11:10│Comments(0)
│開催したイベントの報告