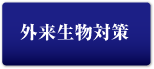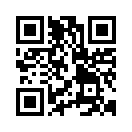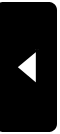2018年03月04日
外来種シンポジウムを開催しました。パネルディスカッションのまとめ
みんなのはままつ創造プロジェクト2017採択事業
【とって食べる】 by昆虫食倶楽部
外来種シンポジウム
外来種って悪者なの? 生物多様性ってなに?
を開催いたしました。(2018/01/20)
前半の五箇さんの講演に続いて、後半はパネルディスカッションです。
まずは外来生物に関する専門家の3氏に、ショートプレゼンをしていただきました。

岸本年郎さん(ふじのくに地球環境史ミュージアム)
外来種対策への批判への批判をしていただきました。
よくある外来種対策への批判は
・外来種が入ることで生物多様性が高くなるのではないか
・外来種の組み込まれた生態系を積極的に認めるべきではないか
・日本は島国だから在来種も元々はすべて外国から来たものじゃないか
・命を奪う行為は許されない
などなど
一見もっともらしく思えますが、大局的に見てみると問題点は多い。
それらよくある外来種対策への批判に対してして、一つ一つ事例、根拠をあげながら批判的コメントをしていただきました。
外来生物対策の活動をしていく上では避けて通れないところなので、私達自身もしっかり自分の言葉として話せるようにしていきたいと思います。
「何を守りたいのか?を明確に意識しよう」とおっしゃっていたのが印象に残っています。
外来種だからといって闇雲に駆除するのではなく、何を守るために、何をどう駆除するのか、科学的な根拠に基づいてしっかりと計画していく必要があります。

片岡友美さん(NPO法人生態工房)
5月に開催した1回目の外来種シンポジウムでアカミミガメ防除の実践について講演していただいた片岡さん
今回はそのダイジェスト版の発表でした。
思えば僕達も1回目のシンポジウムの前までは、アカミミガメについてほとんど知りませんでした。
シンポジウムをきっかけに、佐鳴湖でのアカミミガメ対策の取り組みをスタートさせることができ、さまざまな知識や経験を得ることができました。
片岡さんはアカミミガメが外来種として注目されるずっと前から防除の活動を続けています。
現場で活動されている方の言葉はとても力強く、僕達も勇気をもらいました。

戸田三津夫さん(静岡大学/昆虫食倶楽部)
冒頭の「人間は生態系を破壊してしまう反面、それを悔いて回復させようともする不思議な生き物」という言葉が印象に残っています。
まさにそのとおりだな、と。
しかも、破壊する人と回復する人が別々にいるわけではなく、同じひとりの人がある場面では破壊し、別の場面では懸命に回復しようと活動している。
生物多様性や外来生物の問題について、あらためて根源的な問いを投げかけていただきました。
各々がそれらの問いについて、考え続けることが重要なのだと思います。
続いて、会場の参加者からの質問に答えながらのディスカッション
大人から子供までさまざまな質問に対して専門家のみなさんに答えていただきました。
印象に残っているお話をいくつかご紹介
Q.生物多様性の研究者になりたい、と言われたら何を指導しますか?
生き物のことばかり知っていてもだめ。
生物多様性は人間社会と自然との関わりを考える事が重要なのだから、自然だけじゃなく人間社会のことをしっかり分かっている必要がある。勉強だけじゃなく、社会に出て、客商売などもして、世の中の仕組みを知った上で生物多様性に関わってしてほしい。多面的にいろいろなことにチャレンジしてほしい。
生物愛だけではいくらたくさんあっても使い物にならない。その愛の意味合いを人に伝えられるコミュニケーション力が重要。
外来生物のキャッチアンドリリースについての質問の中でのエピソード
オオクチバスが特定外来生物に指定されるかどうかで、釣愛好団体と環境省、魚類学者等が協議を進めているなかで、某政治家の鶴の一声で指定されることが決まった、という出来事があった。
環境団体ではその政治家を賞賛する声が高まったが、鶴の一声で黒が白になるということは、逆に一声で白が黒にもなり得るということであり、議論をないがしろにするような強引なやり方は、いくらその決定が自分の望むものだったとしても、よろしくない。
Q.外来生物を殺す場面で、その必要性をどう説明するのが良いか
何を守りたいかの優先順位について話す。この外来種がいることによって、本来この場所にいるはずの在来種が生きられない、もしくは死んでしまうから、外来種はいなくなってもらう、という説明をしている。
最近メディアで取り上げられることも増えたので、外来種の被害については理解が少し広がってきていると思う。
そもそも他の生き物を殺さないで生きている生き物はいない。スーパーのお肉は他の人が見えないところで殺す役割をしてくれているだけ。
Q.五箇さんのファッションについて
外来生物問題について、興味がある人に対していくら話しても広がりがない。興味を持ってない人に振り向いてもらって、関心を持ってもらうための仕掛けが必要。バラエティー番組に出演しているのもその一環。NHKクローズアップ現代とバラエティーの脱力タイムズに両方出ることで、両方の視聴者層がつながる。
ただ、それをするためには学者として揺るがない科学的根拠を身につけておくことが絶対に必要。
学者はどうしたらいいかを判断するための科学的根拠を提供するのが仕事。それを材料にして地域の生物多様性について地域の当事者が自分たちで意思決定をするのが本来の姿。
改めて振り返って、とても学びの多い、そして笑いがあふれる楽しいシンポジウムだったな、と思います。
昆虫食倶楽部は【とって食べる】のイベントで「食べる」ことを切り口に身近な自然を「味わって」いるのですが、
「食べる」ことで、外来種対策の活動でも五箇さんのおっしゃるような興味を持っていなかった人を振り向かせる効果があると思いますし、悪者⇔悪者じゃないのようなある種の分断を繋いでいくような役割も担うことができるのではないか、なんて思いました。
この学びを活かして、これからの活動をさらに充実した物にしていきたいと思います。
地域の生物多様性を守るのは、地域住民自身。
興味を持った方は昆虫食倶楽部の活動にもご協力いただけるとうれしいです。

前半の五箇公一さん講演のまとめはこちら
フェイスブック https://www.facebook.com/tottetaberu/
インスタグラム https://www.instagram.com/tottetaberu/
「いいね!」「フォロー」お願いしますm(_ _)m
とる食べ会員募集中です!
詳しくはこちら←クリック
【お問い合わせ先】
昆虫食倶楽部 夏目恵介
電話:090-9900-0928
メール:tottetaberu@gmail.com
【とって食べる】 by昆虫食倶楽部
外来種シンポジウム
外来種って悪者なの? 生物多様性ってなに?
を開催いたしました。(2018/01/20)
前半の五箇さんの講演に続いて、後半はパネルディスカッションです。
まずは外来生物に関する専門家の3氏に、ショートプレゼンをしていただきました。

岸本年郎さん(ふじのくに地球環境史ミュージアム)
外来種対策への批判への批判をしていただきました。
よくある外来種対策への批判は
・外来種が入ることで生物多様性が高くなるのではないか
・外来種の組み込まれた生態系を積極的に認めるべきではないか
・日本は島国だから在来種も元々はすべて外国から来たものじゃないか
・命を奪う行為は許されない
などなど
一見もっともらしく思えますが、大局的に見てみると問題点は多い。
それらよくある外来種対策への批判に対してして、一つ一つ事例、根拠をあげながら批判的コメントをしていただきました。
外来生物対策の活動をしていく上では避けて通れないところなので、私達自身もしっかり自分の言葉として話せるようにしていきたいと思います。
「何を守りたいのか?を明確に意識しよう」とおっしゃっていたのが印象に残っています。
外来種だからといって闇雲に駆除するのではなく、何を守るために、何をどう駆除するのか、科学的な根拠に基づいてしっかりと計画していく必要があります。

片岡友美さん(NPO法人生態工房)
5月に開催した1回目の外来種シンポジウムでアカミミガメ防除の実践について講演していただいた片岡さん
今回はそのダイジェスト版の発表でした。
思えば僕達も1回目のシンポジウムの前までは、アカミミガメについてほとんど知りませんでした。
シンポジウムをきっかけに、佐鳴湖でのアカミミガメ対策の取り組みをスタートさせることができ、さまざまな知識や経験を得ることができました。
片岡さんはアカミミガメが外来種として注目されるずっと前から防除の活動を続けています。
現場で活動されている方の言葉はとても力強く、僕達も勇気をもらいました。

戸田三津夫さん(静岡大学/昆虫食倶楽部)
冒頭の「人間は生態系を破壊してしまう反面、それを悔いて回復させようともする不思議な生き物」という言葉が印象に残っています。
まさにそのとおりだな、と。
しかも、破壊する人と回復する人が別々にいるわけではなく、同じひとりの人がある場面では破壊し、別の場面では懸命に回復しようと活動している。
生物多様性や外来生物の問題について、あらためて根源的な問いを投げかけていただきました。
各々がそれらの問いについて、考え続けることが重要なのだと思います。
続いて、会場の参加者からの質問に答えながらのディスカッション
大人から子供までさまざまな質問に対して専門家のみなさんに答えていただきました。
印象に残っているお話をいくつかご紹介
Q.生物多様性の研究者になりたい、と言われたら何を指導しますか?
生き物のことばかり知っていてもだめ。
生物多様性は人間社会と自然との関わりを考える事が重要なのだから、自然だけじゃなく人間社会のことをしっかり分かっている必要がある。勉強だけじゃなく、社会に出て、客商売などもして、世の中の仕組みを知った上で生物多様性に関わってしてほしい。多面的にいろいろなことにチャレンジしてほしい。
生物愛だけではいくらたくさんあっても使い物にならない。その愛の意味合いを人に伝えられるコミュニケーション力が重要。
外来生物のキャッチアンドリリースについての質問の中でのエピソード
オオクチバスが特定外来生物に指定されるかどうかで、釣愛好団体と環境省、魚類学者等が協議を進めているなかで、某政治家の鶴の一声で指定されることが決まった、という出来事があった。
環境団体ではその政治家を賞賛する声が高まったが、鶴の一声で黒が白になるということは、逆に一声で白が黒にもなり得るということであり、議論をないがしろにするような強引なやり方は、いくらその決定が自分の望むものだったとしても、よろしくない。
Q.外来生物を殺す場面で、その必要性をどう説明するのが良いか
何を守りたいかの優先順位について話す。この外来種がいることによって、本来この場所にいるはずの在来種が生きられない、もしくは死んでしまうから、外来種はいなくなってもらう、という説明をしている。
最近メディアで取り上げられることも増えたので、外来種の被害については理解が少し広がってきていると思う。
そもそも他の生き物を殺さないで生きている生き物はいない。スーパーのお肉は他の人が見えないところで殺す役割をしてくれているだけ。
Q.五箇さんのファッションについて
外来生物問題について、興味がある人に対していくら話しても広がりがない。興味を持ってない人に振り向いてもらって、関心を持ってもらうための仕掛けが必要。バラエティー番組に出演しているのもその一環。NHKクローズアップ現代とバラエティーの脱力タイムズに両方出ることで、両方の視聴者層がつながる。
ただ、それをするためには学者として揺るがない科学的根拠を身につけておくことが絶対に必要。
学者はどうしたらいいかを判断するための科学的根拠を提供するのが仕事。それを材料にして地域の生物多様性について地域の当事者が自分たちで意思決定をするのが本来の姿。
改めて振り返って、とても学びの多い、そして笑いがあふれる楽しいシンポジウムだったな、と思います。
昆虫食倶楽部は【とって食べる】のイベントで「食べる」ことを切り口に身近な自然を「味わって」いるのですが、
「食べる」ことで、外来種対策の活動でも五箇さんのおっしゃるような興味を持っていなかった人を振り向かせる効果があると思いますし、悪者⇔悪者じゃないのようなある種の分断を繋いでいくような役割も担うことができるのではないか、なんて思いました。
この学びを活かして、これからの活動をさらに充実した物にしていきたいと思います。
地域の生物多様性を守るのは、地域住民自身。
興味を持った方は昆虫食倶楽部の活動にもご協力いただけるとうれしいです。

前半の五箇公一さん講演のまとめはこちら
フェイスブック https://www.facebook.com/tottetaberu/
インスタグラム https://www.instagram.com/tottetaberu/
「いいね!」「フォロー」お願いしますm(_ _)m
とる食べ会員募集中です!
詳しくはこちら←クリック
【お問い合わせ先】
昆虫食倶楽部 夏目恵介
電話:090-9900-0928
メール:tottetaberu@gmail.com
Posted by 昆虫食倶楽部 at 01:12│Comments(0)
│開催したイベントの報告